芦田愛菜さんといえば、子役時代から活躍し、現在は女優として幅広い活動を展開している才能豊かな若手女優です。
そんな芦田さんですが、実は驚異的な読書量を誇る本の虫としても知られていますが、どんな本が好きなのでしょう?
今回は、芦田さんの読書愛に迫りながら、彼女の人生を変えた1冊についても探っていきたいと思います。
それでは早速本題に入っていきましょう!
芦田愛菜の驚異的な読書量と読書愛

芦田愛菜さんの読書量は、多くの人を驚かせるほど膨大です。
結論から言えば、芦田さんは自称「活字中毒」と呼べるほどの読書家であり、その読書量は一般人の想像を遥かに超えています。
具体的な数字を見てみると、中学生時代には年間300冊以上、現在の高校・大学時代でも年間100冊以上を読破しているそうです。
さらに驚くべきことに、小学生時代でさえ年間60冊(一説には月50冊)を読んでいたといいます。
この驚異的な読書量の根拠として、芦田さん自身の言葉があります。
彼女は「本がなければ成分表でも読みまくる」と語っており、読書が歯磨きやお風呂と同じように生活の一部になっていると明かしています。
このエピソードからも、芦田さんの読書への情熱が伝わってきますね。
芦田さんの読書愛は、2019年に出版された『まなの本棚』という著書にも表れています。
この本の中で、芦田さんは約100冊もの本を厳選して紹介しており、それぞれの本に対する深い愛情と洞察が感じられます。
読者としては、芦田さんの読書量の多さに圧倒されると同時に、彼女の知的好奇心の強さに感銘を受けずにはいられません。
芦田愛菜のジャンル別おすすめ本

芦田愛菜さんの好きな本は、ジャンルを問わず多岐にわたります。
結論として、芦田さんは小説から古典文学、児童文学、さらには学術書まで幅広いジャンルの本を愛読していることがわかるのです。
小説・文学作品の分野では、辻村深月さんの『ツナグ』や『かがみの孤城』、村上春樹さんの『騎士団長殺し』などが挙げられます。
特に『ツナグ』については、「好きすぎて本当は教えたくなかった本」と語るほど強い愛着を持っているようです。
古典・日本文学の分野では、森鴎外の『舞姫』や『高瀬舟』、夏目漱石の『坊ちゃん』などを愛読しています。
『舞姫』は芦田さんにとって「古典文学の面白さに目覚めさせてくれた本」だったそうです。
このエピソードから、芦田さんが若くして古典文学の魅力に気づいていたことがうかがえます。
児童文学・ファンタジーの分野では、『ハリー・ポッター』シリーズや『不思議の国のアリス』が挙げられます。
特に『ハリー・ポッター』については、「小学生の時から大好きで、いまだによく読み返している」と語っており、芦田さんの長年の愛読書であることがわかりますよね。
11歳の時に「ホグワーツからの入学許可証が届かなかった」と、がっかりしたというエピソードは、芦田さんの純粋な読書愛を感じさせます。
芦田愛菜の読書スタイルと本から学んだこと

芦田愛菜さんの読書スタイルは、彼女の人生観や価値観に大きな影響を与えているのです。
芦田さんは読書を通じて物事の多面的な見方や想像力の重要性、言葉の美しさ、人生の深さを学んでいることがわかります。
芦田さんの読書への取り組み方は、「本との出会いは宝探し」というフレーズにも集約されているのです。
その時の気分で直感的に本を選び、空き時間があれば自然と本を手に取るという習慣が、彼女の「活字中毒」レベルの読書量につながっているのでしょう。
また、芦田さんは「紙の本愛好家」としても知られています。
本の手触りや匂い、ハードカバーを開く音までも愛しているという芦田さんの姿勢は、デジタル全盛の現代において、アナログの良さを再認識させてくれますよね。
さらに、気に入った本は何度も読み返す「再読主義者」でもあるそうです。
芦田さんが、本から学んだことの中で特筆すべきは、「物事の多面的な見方」でもあります。
例えば、今村夏子さんの『星の子』を読んで、「物事の多面的な見方」を学んだとも。
このエピソードは、芦田さんが単に物語を楽しむだけでなく、そこから人生の教訓を得ようとする姿勢を持っていることを示しています。
まとめ
芦田愛菜さんの読書愛は、単なる趣味を超えて人生の一部となっています。
幼少期からの継続的な読書習慣、ジャンルを問わない幅広い読書、本から学んだことを実生活に活かす姿勢、そして読書を通じた感性の育成。
これらの要素が組み合わさって、現在の芦田さんの魅力的な人格が形成されたと言えるでしょう。
芦田さんの読書習慣は、私たちに読書の素晴らしさと、知的好奇心を持ち続けることの大切さを教えてくれています。
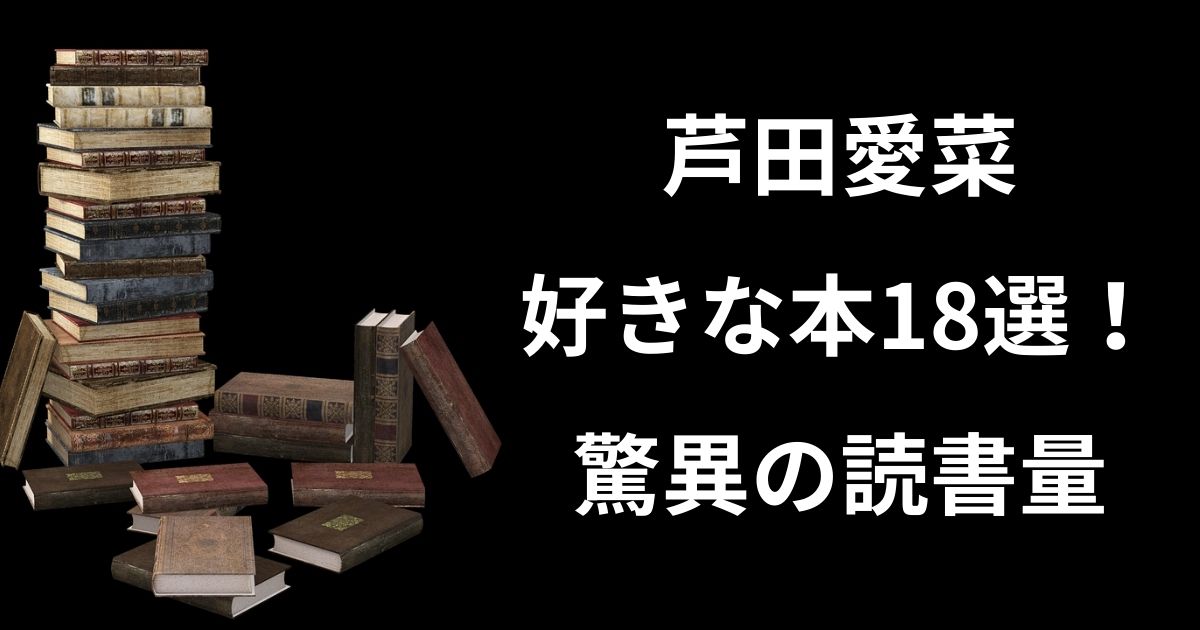
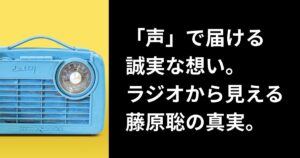

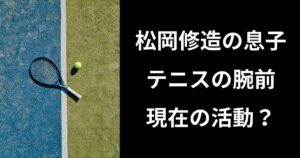
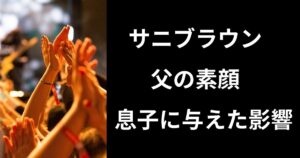
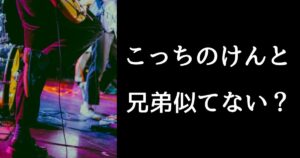

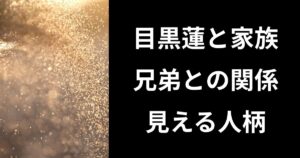
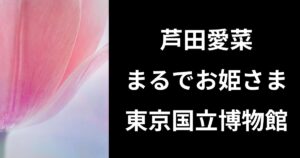
コメント