古民家の玄関を開けた瞬間、ひんやりとした空気と土壁の匂いが広がった。
都会では味わえない「時間の止まり方」に、思わず深呼吸したのを覚えている。
電気の通りが悪く、夜になると真っ暗。
それでも、その暗さがなぜか心地よかった。
タサン志麻さんが古民家で暮らし始めたというニュースを見て、あの静けさを思い出した。
便利さを手放すことで見えてくる“暮らしの本質”があるのかもしれない。
古民家との出会いがくれた静かな衝撃

移住を考え始めたのは、「もっと自分のペースで暮らしたい」と思ったからだった。
古民家に初めて足を踏み入れた瞬間、時代の重みと人の気配がまだ残っていることに気づいた。
柱に刻まれた小さな傷、すり減った床、色あせた障子。どれも過去の生活の名残だ。
タサン志麻さんも、築百年を超える古民家を自らの手で整えながら「完成しない家が好き」と語っている。
この“未完成の美しさ”に共感した。
最初の夜、虫の声がうるさいほど響き、電灯一つの明かりで過ごした。
でも、夜が更けるにつれて“静けさの層”が何重にも重なっていく感覚があった。
不便の中にある静けさが、心の中のざわめきを鎮めてくれる。
それが、古民家暮らしの最初の贈り物だった。
不便さの中にこそ、暮らしのリズムが生まれる

便利さを求め続けた生活から離れると、最初は戸惑いの連続だった。
けれど、不便さは「手を動かす理由」を与えてくれる。
それが、暮らしにリズムをもたらしてくれるのだ。
蛇口をひねれば水が出る、スイッチを押せば暖かい。
そんな便利な日常の裏で、“自分の時間を失っていた”ことに気づく。
志麻さんが「料理は段取りではなく、暮らしの延長」と語るように、家事や手入れそのものが、心を整える儀式になる。
朝、窓を開けると、鳥の声とともに湿った空気が流れ込んでくる。
炊事を終えるころには、庭の草木が陽を浴びて揺れている。
“便利”の外側にこそ、本当の豊かさがある。
それに気づいてからは、時間の流れがゆっくりと身体に馴染んでいった。
暮らしは完成しなくていい

古民家を直す作業は、思っていた以上に果てしない。
それでもいい。
“完成しない暮らし”の中に、成長と発見がある。
壁を塗りながら、木の節や釘の跡に前の住人の手仕事を感じる。
志麻さんも、「暮らしを整えるのに終わりはない」と語っていた。
完璧ではない日々が、人の心をやわらかくしてくれるのだ。
DIYの途中のままの廊下、剥がれかけた襖。
それでも、夕方の光が部屋の奥まで届くとき、ふと“この家が息をしている”と感じる。
暮らしを育てることは、自分を育てること。
古民家の木の香りが、それを静かに教えてくれる。
まとめ:不完全な暮らしが、心を満たしてくれる
古民家暮らしは、手間がかかる。
でも、その手間のひとつひとつが「生きている実感」につながる。
タサン志麻さんのように、完成を目指さず、日々を味わいながら生きていく。
便利さを手放した先にある“ゆるやかな幸せ”を、これからも見つけていきたい。
🔗 拡散用情報(SNS・サムネ用)
タサン志麻さんの古民家暮らしに共感!
不便だけど豊かな、静かな時間の中で見つけた幸せ。
暮らしは完成しなくていい——そんな生き方を始めました。
#タサン志麻 #古民家暮らし #スローライフ #田舎移住
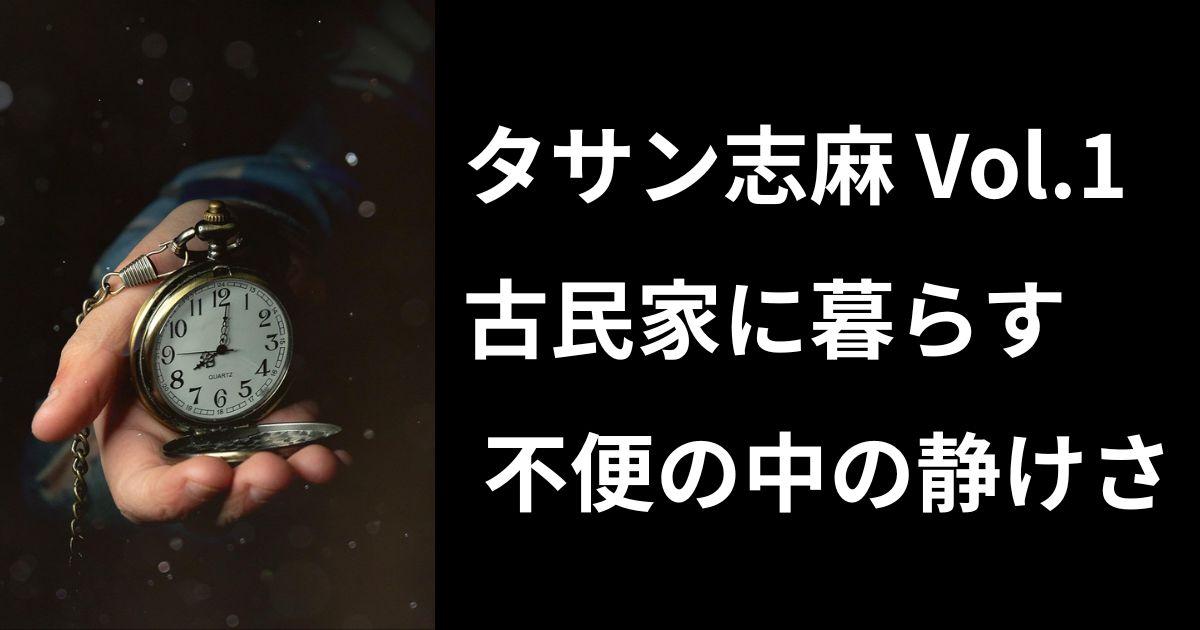
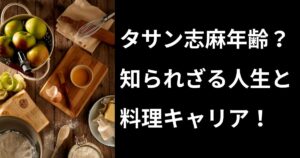


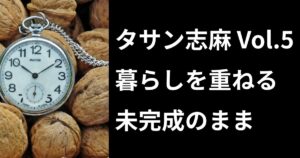
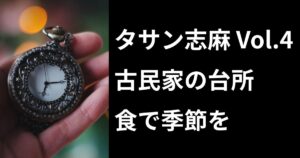
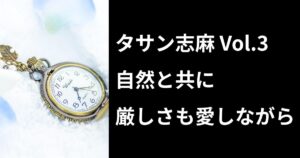
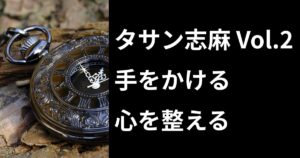
コメント