朝、台所の窓を開けると、外の光がまぶしく流れ込む。
湯気の向こうには、炊き立てのごはんと、味噌汁の香り。
静かな空間の中で、包丁の音だけが響く。
この小さな台所が、一日の始まりを整えてくれる。
タサン志麻さんが「料理は特別なことではなく、暮らしの延長」と語るように、古民家の台所には、手間とやさしさが溶け合う時間がある。
旬の食材が“暮らしのカレンダー”になる

田舎で暮らすようになってから、季節の移り変わりを食材で感じるようになった。
旬の食材は、カレンダーよりも正確に“季節の訪れ”を教えてくれる。
春には山菜、夏はナスやトマト、秋は栗ときのこ、冬は大根や根菜。
スーパーの棚ではなく、畑や直売所で出会う食材たち。
タサン志麻さんも、料理番組で「旬を味わうことが心のリズムになる」と語っていた。
旬の食材を手にしたとき、自然のサイクルの中に自分も生きていることを実感する。
初夏の朝、庭の梅をもいで梅シロップを仕込んだ。
瓶に詰める瞬間、氷砂糖が太陽に反射してきらめいた。
一か月後、透き通るような琥珀色になったシロップを味見したとき、「季節を待つ」という贅沢を知った。
手をかける台所仕事が、心を整える

台所では、いつも小さな作業が繰り返される。
皮をむく、切る、煮る、洗う——それだけのことなのに、心が落ち着いていく。
手を動かすことが、心を整える時間になる。
志麻さんは「段取りではなく、流れを大切にする」と話している。
レシピ通りに進めるよりも、音・香り・温度を感じながら作る。
それが、“生きた料理”になる。
古民家の台所は狭くても、光と風が通り抜けるだけで十分だ。
夕方、土鍋でご飯を炊いていると、台所に光が差し込んだ。
その光の中で、お米の湯気がゆらゆらと立ちのぼる。
「今日はうまく炊けたな」と思うだけで、心が軽くなる。
料理は、誰かのためだけでなく、自分を癒やす行為でもある。
食卓が“家族の時間”をつなぐ

どんなに忙しい日でも、食卓だけは家族が集まる場所にしている。
手作りの料理が並ぶ時間は、暮らしの中でいちばんあたたかい瞬間だ。
志麻さんの家でも、フランス出身の夫と子どもたちが揃う食卓が日常。
「食べることは、話すことと同じくらい大切」と語る。
その言葉に、古民家の食卓の意味を重ねたくなる。
湯気、笑い声、そして箸の音——それだけで“今日もいい日”になる。
ある晩、煮物を囲みながら子どもが「この味、昨日と違うね」と言った。
思わず笑って、「それが手作りの面白さだよ」と答えた。
同じ材料でも、気温や気分で味が変わる。
それが、暮らしの“生きもの”らしさ。
まとめ:台所は家の心臓、暮らしの温度計
古民家の台所は、派手さも最新設備もない。
けれど、そこには暮らしの“鼓動”がある。
タサン志麻さんのように、食を通して人と自然をつなぐこと。
それが、この家での暮らしの中心になっている。
今日もまた、火を起こし、鍋を温め、旬を味わう。
その繰り返しが、何よりの幸せだ。
🔗 拡散用情報(SNS・サムネ用)
タサン志麻さんの古民家の台所から学ぶ、
“旬を味わい、暮らしを整える”時間の魔法。
手を動かすたびに、心まで温まる。
#タサン志麻 #古民家暮らし #台所のある暮らし #季節の食卓
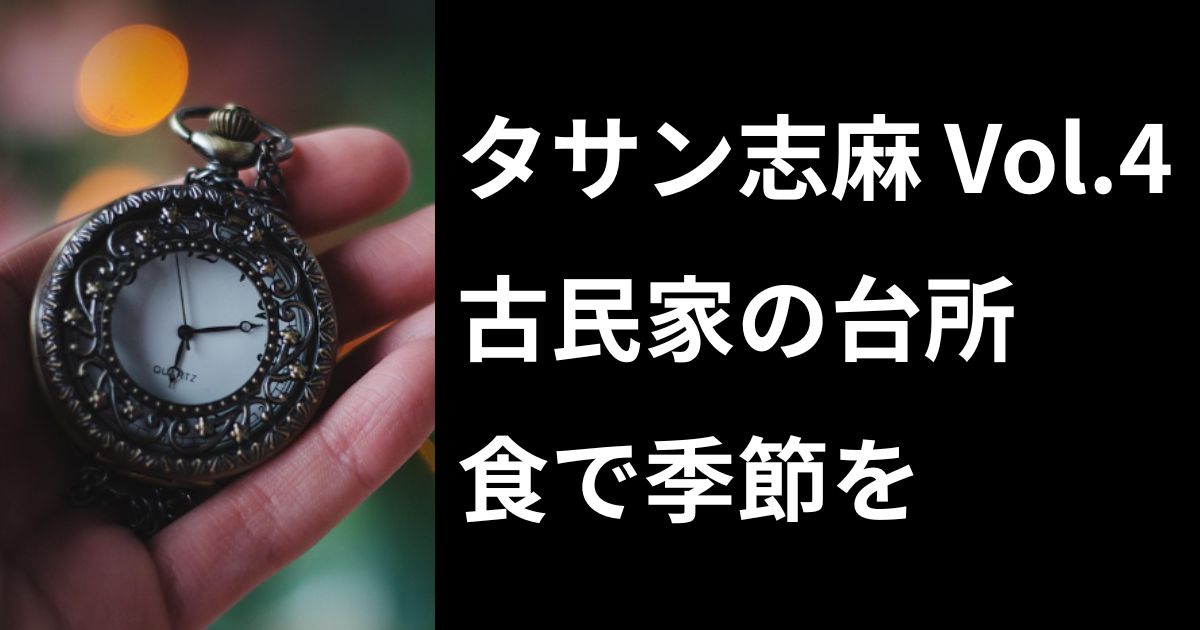
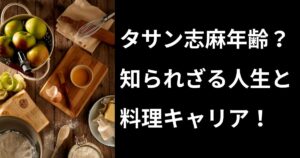


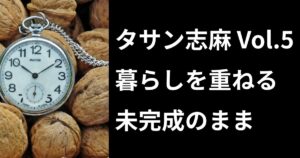
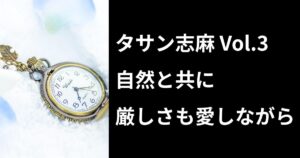
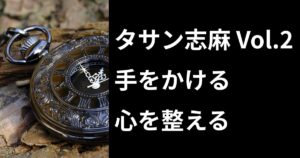
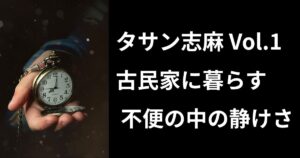
コメント