スマホ決済や電子チケットなど、私たちの生活にすっかり定着したQRコード。
便利な一方で、最近はこの仕組みを悪用した新しい詐欺「クイッシング(Quishing)」が急増しています。
メールやポスター、SNSなど身近なところから仕掛けられるため、気づかないうちに被害に遭う人も少なくありません。
ここでは、クイッシングの仕組みや実際の事例、そして今日からできる安全対策までをわかりやすく紹介します。
知らないと危険!クイッシングとは何か

知らぬ間に個人情報が「クイッシング」とは、QRコードを利用して個人情報を盗み取る詐欺のことです。
名前の由来は「QRコード(Quick Response)」と「フィッシング(Phishing)」を組み合わせた言葉で、メールやSNS、チラシなどに載せられたQRコードを読み取らせ、偽物のサイトに誘導する手口が一般的です。
そこにパスワードやクレジットカード番号を入力してしまうと、情報がそのまま盗まれてしまう危険があります。
特に怖いのは、見た目が本物そっくりな点です。
企業ロゴや色使いまで巧妙に再現されており、信頼できる情報に見えてしまうことが多いのです。
「フィッシング詐欺」と似ていますが、メールのリンクではなくQRコードを“入り口”にする点が異なります。
リンクに警戒しても、QRなら安全だと思い込みやすい心理を狙うのがクイッシングの特徴です。
最近この被害が増えている背景には、QRコード決済や電子チケットなど、私たちの生活にQRコードが深く入り込んだことがあります。
「簡単」「便利」と思うその習慣が、詐欺師にとって格好のチャンスになっているのです。
さらにAIや画像編集ツールの発達で、偽コードの作成が簡単になったことも影響しています。
つまり、誰もが狙われる可能性があるということです。
実際に起きた国内のクイッシング被害事例3選

具体的な被害事例を見ると、その巧妙さがよく分かります。
ある大手自動車用品販売会社では、「会員情報の更新をお願いします」というDM(ダイレクトメール)が顧客に送られました。
内容は本物のように見えましたが、QRコードを読み取ると偽のサイトへ誘導され、個人情報を入力させる仕組みになっているのです。
被害者の中には、クレジットカード情報を登録してしまった人もいたそうです。
また、福岡市内では「アンケートに答えるとクーポン進呈」と書かれたチラシが配布され、そこに印刷されたQRコードを読み取ると偽サイトにアクセスしてしまう事件が発生しました。
中には、街中の正規ポスターの上から偽QRを貼り付ける悪質なケースもあり、一般の人が見分けるのは困難です。
さらにSNS上でも、「有名ブランドのキャンペーン実施中!」という投稿にQRコードが添付され、応募フォームを装った偽サイトへ誘導される事例も相次いでいます。
信頼できる友人がリポストしていることで、安心してしまう人も多く、SNSならではの“つながりの信頼”が悪用されていることも。
公式アカウントを装った詐欺も多いため、公式マークの有無やURLのドメイン名を確認する習慣が欠かせません。
クイッシング被害を防ぐための5つの対策

まず何よりも大切なのは、怪しいQRコードを読み取らないことです。
差出人が不明なメールや、街角のポスター、SNS投稿に貼られたQRコードなど、出どころがわからないものは避けましょう。
「限定」「無料」「今すぐ」といった言葉で急がせる内容は、詐欺の常套句です。
次に、QRコードを読み取る際はスマホ標準のカメラアプリか、信頼できる公式アプリを利用してください。
不明なQRリーダーアプリの中には、アプリ自体が個人情報を抜き取る危険なものもあります。
また、表示されたURLが「https://」(暗号化され、保護されている)で始まっているかを必ず確認しましょう。
鍵マークのないサイト「http://」(暗号化されていない)は入力を控えるのが鉄則です。
さらに、多要素認証(2段階認証)を設定しておくことで、不正ログインを防ぐことができます。
もし偽サイトにIDやパスワードを入力してしまっても、追加認証があることで被害を最小限に。
セキュリティツールやWEBフィルタを活用して、危険なサイトを自動でブロックする設定も有効です。
そして、家族や職場など周囲と情報を共有することも重要になります。
高齢者や子どもはQRコードの危険性を知らないことも多いため、「こういう詐欺があるらしいよ」と日常的に声をかけ合うだけでも、被害を防げる可能性が高まるのです。
QRコード利用時に注意すべき3つのポイント

クイッシングは紙のチラシだけでなく、スマホの画面やメールの中にも仕掛けられています。
特に「荷物の再配達」「口座確認」「キャンペーン当選」などを装ったメールにQRコードが添付されていたら注意しましょう。
正規の企業は、メール本文に直接QRコードを載せることはほとんどありません。
必ず公式アプリや公式サイトからアクセスするようにしてください。
また、「完璧な防御策はない」という前提を理解しておくことも大切です。
詐欺の手口は常に進化しており、100%の安全は存在しません。
大切なのは、「疑って確認する」という小さな習慣です。
QRコードを読み取る前に「誰が発行したものか」「本当に必要な操作か」を一度考えるだけで、被害は大幅に減らせます。
さらに、最新の詐欺情報に常にアンテナを張ることも忘れずに。
警察庁やセキュリティ企業の公式サイトでは、最新の手口や注意喚起が随時更新されています。
SNSでも、信頼できる情報源をフォローしておくと、危険な動きを早めに察知できます。
もしクイッシング被害に遭ってしまったら

万が一、怪しいQRコードを読み取ってしまった場合は、すぐに対応することが何より重要です。
まずは入力したパスワードをすぐに変更し、同じパスワードを他のサイトで使っている場合はすべて変更しましょう。
その後、セキュリティアプリで端末をスキャンし、ウイルス感染がないかを確認します。
クレジットカード情報を入力してしまった場合は、速やかにカード会社や金融機関に連絡を。
利用停止や再発行の手続きを依頼すれば、被害の拡大を防げます。
あわせて、最寄りの警察署や「サイバー犯罪相談窓口」にも報告しておくと安心です。
不安な場合は、利用履歴やメールの送信履歴などを確認し、不審な動きがないかチェックしましょう。
早い段階で対応すれば、金銭的被害を防ぐ可能性が高まります。
まとめ:便利なQRコードを“安全に使う”意識を持とう
QRコードは、支払いも情報取得も一瞬でできる便利な仕組みです。
しかしその手軽さの裏には、「誰でも偽コードを作れるリスク」が潜んでいます。
クイッシングのような詐欺から身を守るためには、知識と注意が最大の防御です。
少しでも不審に感じたら読み取らない、URLを確認する、家族や仲間に情報を共有する──その積み重ねが自分を守ります。
詐欺は“知れば防げる”ものです。
便利さとリスクを正しく理解し、安心してQRコードを活用できる社会を、一人ひとりの意識でつくっていきましょう。
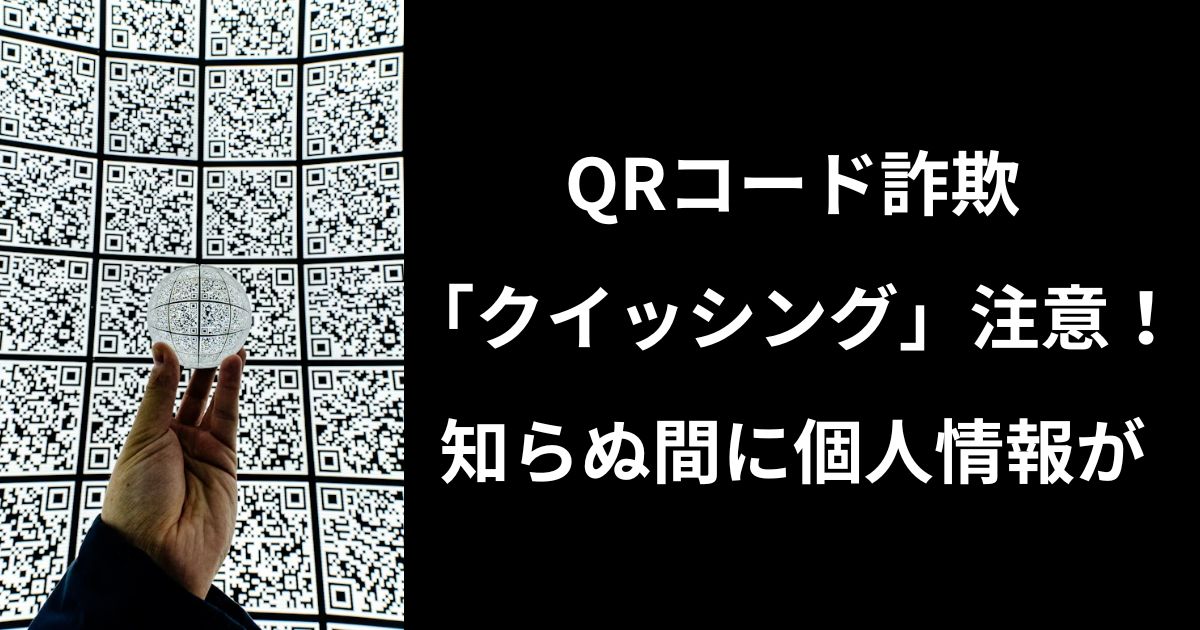
コメント