藤井風さんの海外進出のニュースが報じられたとき、多くの音楽ファンの頭に浮かんだのは、ある一人の名前だったのではないでしょうか。
──宇多田ヒカルさん。
日本語と英語の狭間で、世界に通じる音楽を作り続けてきた先駆者ですが、その活躍を比べてみたいと思いませんか?
この記事で、二人の歩みを重ねていくと、単なる「海外志向」ではない、“言葉と音の融合”という共通テーマが見えてきます。
それでは早速本題に入っていきましょう!
宇多田ヒカルの「バイリンガル表現」──言葉を超える音楽の力

宇多田ヒカルさんは、デビュー当初から日本語と英語の間を軽やかに往復してきたアーティストです。
どちらの言語も「使うもの」ではなく「響かせるもの」として扱う。
その姿勢が、彼女の音楽を唯一無二の存在へと押し上げました。
代表作『Automatic』や『First Love』では、日本語の美しいリズムを守りながら、英語的な音の流れを自然に溶け込ませる手法が光ります。
彼女の音楽は、国や言葉の枠を越えて、“感情そのもの”を音に変える表現なのです。
2004年の英語詞アルバム『Exodus』を皮切りに、宇多田さんは「言葉の意味」ではなく「言葉の音」を探る試みを続けてきました。
発音や語尾の処理はネイティブらしさよりも“響きの流れ”を優先。
その結果、どの楽曲にも共通する「言葉と旋律の一体感」が生まれています。
特にライブでは、英語詞の曲でも“日本語の呼吸”が感じられる瞬間があります。
音楽が言葉を超えて心に届くとは、こういうことかと気づかされます。
宇多田ヒカルさんの音楽には、母国語も国境も存在しません。
ただ“感情の温度”だけが聴き手の胸に残る不思議な感覚があると思います。
藤井風の「Prema」に見る英語詞の挑戦

そんな宇多田ヒカルさんが築いた「言葉と音の融合」の道を、次の世代として受け取ったのが藤井風さんです。
彼の最新作『Prema』は、まさに“言葉を音に変える試み”の進化形といえるでしょう。
2025年9月に発表された『Prema』は、藤井風さんにとって初の本格的な英語詞アルバム。
アメリカの大手レーベル Republic Records との契約により、制作・配信の両面で世界基準の体制を整えた一作です。
ただし、彼が英語を選んだ理由は“海外で売れるため”ではありません。
英語の柔らかな母音や息の流れ、リズムの余白が、彼にとって“感情を音に変える最適なツール”だったのです。
言葉を翻訳するのではなく、感情そのものを響かせる――そのアプローチが『Prema』全体を包んでいます。
『Prema』を聴くと、英語がまるで旋律の一部になっているのがわかります。
どの曲も透明で、どこか祈りのような穏やかさがある。
英語を「学んだ言葉」ではなく「感じる音」として扱うその姿勢に、藤井風さんの音楽家としての自由さを感じます。
それはまるで、宇多田ヒカルさんの“響きの哲学”に新しい光を当てたようにも感じます。
言葉と魂の共鳴──ふたりの「言葉を選ぶ覚悟」

宇多田ヒカルさんと藤井風さん。
ふたりはどちらも、言葉を単なる伝達手段としてではなく、“心の翻訳”として扱う音楽家です。
彼らが重視しているのは、「伝わること」よりも「響くこと」。
英語は世界に届くが、感情の繊細さが薄れやすい。
日本語は感情を深く伝えられるが、世界には届きにくい。
その矛盾をどう乗り越えるか――そこにふたりの挑戦の本質があります。
宇多田さんは、二つの言語を自在に行き来する“詩人”。
藤井風さんは、一つの心で二つの言葉を歌う“祈り人”。
どちらも「言葉を音に変える」方法は違えど、言葉の重さと脆さを知り尽くしているからこそ、英語でも日本語でも聴く人の心を震わせる力を持っています。
宇多田さんの『Beautiful World』を聴いたとき、「英語でも日本語でもない、感情そのものの歌だ」と感じたことがあります。
藤井風さんの『Hachikō』にも、同じ“非言語の響き”が漂っています。
ふたりが歌うのは、言葉ではなく“魂のリズム”。
それが聴き手に直接届くから、国や文化を超えて共感を呼ぶのですね。
まとめ:言葉を超える、音楽という共通語
二人に共通しているのは、言葉を操る冷静さと、言葉を超えた場所で“心を届けたい”という誠実さでした。
音楽を言語の外側にある“人間の感情”として描こうとしています。
英語でも日本語でもない――ただ“音”として伝わる瞬間。
そのとき、聴く人は言葉を理解するのではなく、感情を感じています。
宇多田ヒカルさんと藤井風さんの音楽は、まさにその瞬間を生み出すためにあるのですね。
それこそが、彼らが追い続けている真のグローバル・ミュージックなのかもしれません。
このあとに続く
→[ 【画像】藤井風と椎名林檎感情を操る?“表現者”としてのルーツと色気! ]
つづく記事は、それぞれ単独でも読めるよう構成されていますが、
順番に読むことで“藤井風というアーティスト像の立体像”が見えてきます。
1️⃣ 米津玄師編 → 「 音楽づくりの方法 」
2️⃣ 宇多田ヒカル編 → 「 言葉とメッセージ 」
3️⃣ 椎名林檎編 → 「 表現と感情 」
🌏 藤井風 × 比較シリーズ→「 日本の音楽が、世界を見据えるとき 」
音楽を知る人にも、これから聴く人にも、
藤井風という名前の奥にある“人間としての物語”が伝わるシリーズになっています。
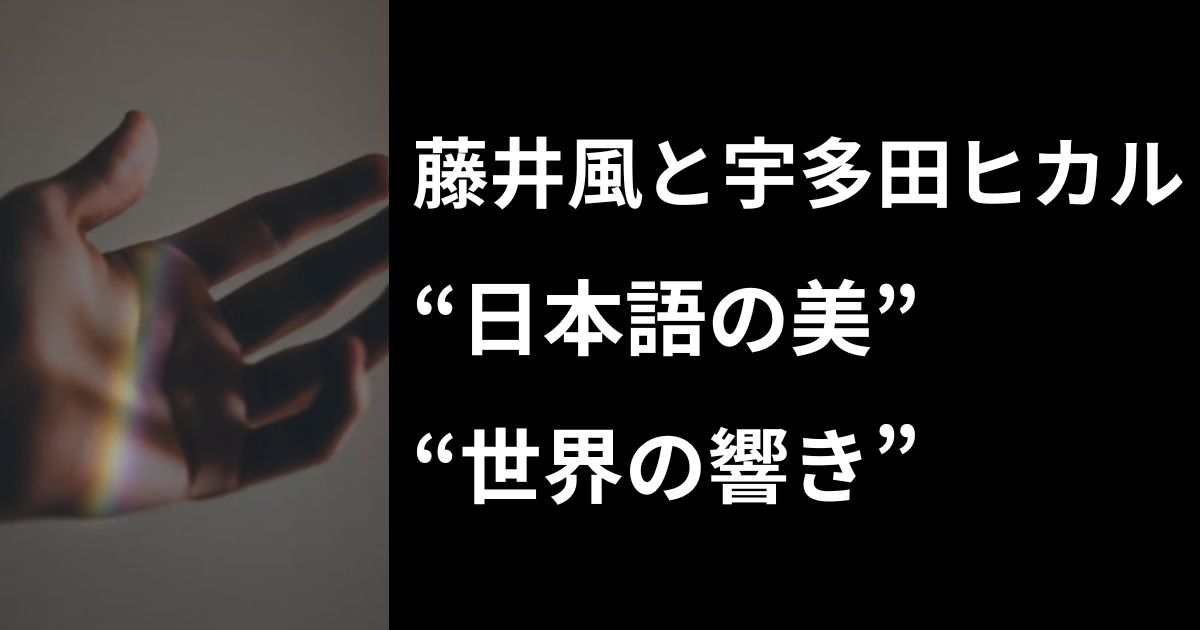
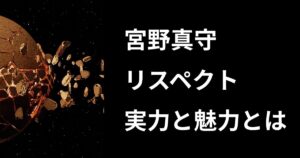

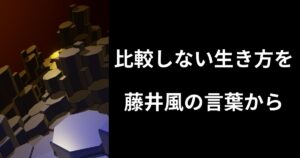

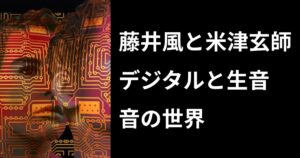

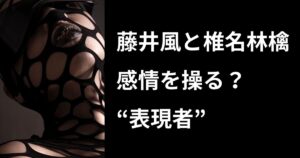

コメント