退職の意志を会社に伝えられない人に代わって手続きを進めてくれる「退職代行サービス」。
ここ数年で利用者が急増し、いまや一般的なサービスとして広く知られるようになりました。
そして2025年10月、人気サービス「モームリ」の運営会社が弁護士法違反(非弁行為)の疑いで警視庁の強制捜査を受けたことで、このテーマが一気に注目を集めました。
今回の出来事は、弁護士の仕事と、民間の代行サービスの“境界線”をあらためて考えるきっかけになっています。
ここでは、弁護士の業務範囲と退職代行サービスの違いを、できるだけ分かりやすく整理してみましょう。
弁護士しかできない“交渉行為”がある

退職代行サービスは、依頼者の代わりに「退職します」という意思を会社へ伝えることができます。
しかし、退職の条件を交渉したり、残業代の支払いを求めたり、損害賠償の話し合いをしたりすることは、弁護士でなければできません。
なぜなら、こうした行為は「法律に関わるやり取り=法律事務」にあたるため、弁護士資格を持つ人だけに認められているからです。
つまり、「退職を伝える」と「条件を交渉する」はまったく別のこと。
もしこの線を越えてしまうと、“非弁行為”と呼ばれる違法行為になるおそれがあります。応できる範囲に明確な違いがあります。
弁護士法が定める「代理・仲裁」の制限
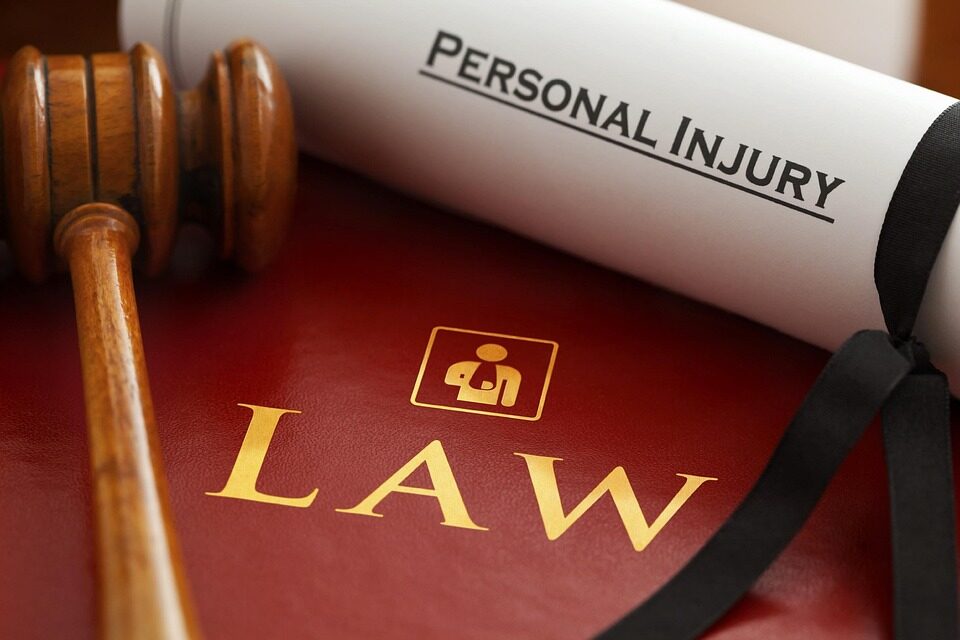
日本の法律では、弁護士でない人が“お金をもらって法律に関わる仕事をする”ことは禁止されています。
これは「弁護士法第72条」という決まりで、たとえば次のような行為が対象になります。
- 依頼者の代わりに会社と条件を話し合う
- 未払い給料や残業代の交渉をする
- トラブルや示談の仲裁をする
これらはすべて「法律事務」にあたるため、弁護士だけが行える仕事です。
そのため、「弁護士監修」「弁護士の指導のもと運営」などと書かれていても、実際のやり取りを一般スタッフがしている場合は、法律違反になる可能性があります。
つまり、“弁護士監修”という言葉があっても、必ずしも「弁護士本人が対応してくれる」という意味ではありません。
今回の事件でも、「弁護士が関わっていると思って依頼したのに、実際は違った」という声が上がっています。
信頼される“法的サポート”の形とは

退職代行サービスは、上司や会社に直接言いづらい人を救う役割も担っています。
特に、パワハラや過重労働に悩む人にとっては、精神的な支えになる存在です。
ただし、法的な知識が不十分なまま業務を行うと、逆に利用者が損をするケースもあります。
例えば、退職条件の交渉が不十分だったり、書類のやり取りで不備が生じたりすることも。
一方で、弁護士法人が直接対応する退職代行では、法律の専門家がトラブル対応まで行うため、「安心感がある」と評判です。
これからは、“代わりに伝える”だけでなく、“法的リスクもカバーする”サービスが信頼される時代になりそうです。
まとめ
退職代行を利用する際は、料金の安さやスピードだけで判断しないことが大切です。
「弁護士が本当に対応してくれるのか」「交渉まで任せられるのか」を確認することで、トラブルを防ぐことができます。
今回の強制捜査は、利用者だけでなく、業界全体が“正しいサポートの形”を見直すきっかけになりそうです。
安心して新しい一歩を踏み出すために、法のルールを知ることが何よりの自衛になるでしょう。

コメント