朝、薪ストーブに火をつけるところから一日が始まる。
マッチの火が木片にうつり、ぱちぱちと音を立てて炎が広がっていく。
湯が沸くまでの数分間、ぼんやりとその炎を見つめる時間がある。
その“何もしない時間”こそが、心を整えてくれる。
タサン志麻さんが「暮らしの中で手間を惜しまない」と語る理由が、少しわかった気がした。
手間は“面倒”ではなく“豊かさ”だった

都会で暮らしていた頃、家事は「いかに早く終わらせるか」がすべてだった。
けれど、古民家に移ってからは“手間”こそが暮らしを支えるリズムになった。
洗濯は晴れた日に外で干し、野菜は皮まで使い切る。
炊飯器の代わりに土鍋でご飯を炊くと、部屋中に湯気と香りが広がる。
少し時間はかかるけれど、その過程の一つひとつが「暮らしを味わう瞬間」になる。
タサン志麻さんも、フレンチの技法をベースにしながら、家庭の手料理を大切にしている。
効率よりも“心の余裕”を優先する姿勢に、深く共感する。
ある日、鍋の焦げを落としながら「時間がもったいない」と思った。
でも、磨き終わった鍋に光が戻ったとき、不思議と自分の気持ちまで晴れていた。
手間をかけることは、物をきれいにするだけでなく、自分を整える行為でもあるのだ。
不便が教えてくれる“暮らしの速度”

古民家では、便利な家電が思うように使えないことも多い。
だからこそ、暮らしの速度が“自然のリズム”に戻っていく。
天気によって洗濯の予定が変わり、季節によって寝具を変える。
「風が冷たいから今日は火を起こそう」「陽が長いから外で食べよう」
そんな小さな判断の積み重ねが、季節とつながる感覚を取り戻してくれる。
志麻さんも「便利さの中では感じられない“暮らしの体温”がある」と語っていた。
電子レンジを使わず、前日の煮物を鍋で温め直した朝。
湯気と一緒に立ちのぼる香りが、昨日の自分を思い出させてくれた。
“急がない暮らし”には、時間の流れを感じる余白がある。
“効率”を手放した先に見えた幸せ

一度“効率”の世界から離れてみると、見えてくるものがある。
それは、「完璧じゃなくても、今を大切にできる」という心の自由だ。
家の中が散らかっていても、土間に靴が並んでいても、それも“生きている証拠”。
手を抜くことと、丁寧に生きることは、同じ線上にある。
志麻さんの古民家も、完成を急がず「少しずつ直していく」スタイル。
その姿勢は、現代の“暮らしの在り方”へのメッセージのように思える。
夕方、薄暗い台所で食器を洗っていると、外の木々がオレンジに染まっていた。
その光がガラス越しに差し込み、シンクをやさしく照らす。
その瞬間、時間が止まったように感じた。
「今日も手を動かせた」
それだけで、十分に満たされた。
まとめ:手を動かす時間が、心を動かす時間になる
古民家の暮らしは、毎日がちょっとした作業の連続だ。
けれど、効率を求めないことで、暮らしがゆっくりと心に染みていく。
タサン志麻さんが教えてくれるのは、「完璧よりも、味わうこと」。
手をかける贅沢を知った今、もう元のスピードには戻れない。
🔗 拡散用情報(SNS・サムネ用)
“手をかける”ことの贅沢。
効率よりも心を整える時間を大切にしたい。
タサン志麻さんの古民家暮らしに学ぶ、手間を愉しむ日々。
#タサン志麻 #古民家 #スローライフ #丁寧な暮らし

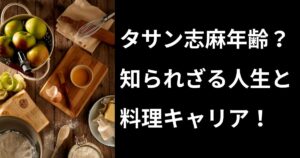


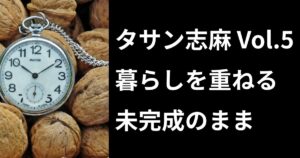
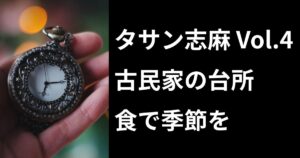
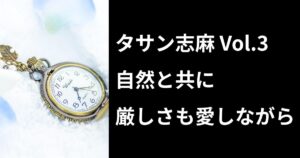
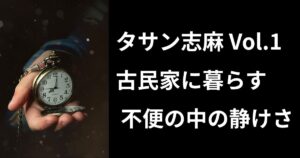
コメント