古民家に住み始めてから、季節が三度めぐった。
壁の塗り跡、欠けた柱、ペンキのはみ出し……それらを見ても、もう気にならなくなった。
むしろ、それらが“暮らしの記録”のように思える。
タサン志麻さんが「家は完成しなくていい」と語っていた意味が、ようやくわかってきた。
暮らしとは、終わりのない“手仕事”なのだ。
未完成の家にこそ、暮らしの息づかいがある

「完成」を目指すほど、暮らしは窮屈になる。
少し歪んだ棚や、塗りむらのある壁にこそ、人の温度が残る。
古民家では、思うようにいかないことが日常だ。
一度直したはずの屋根がまたきしみ、塗った壁が雨で少し剥がれる。
けれど、それを“失敗”とは感じなくなる。
タサン志麻さんも「暮らしを直すこと自体が楽しい」と笑っていた。
完璧を手放すと、家が少しずつ“生き物”のように見えてくる。
ある日、子どもが床の隙間に小石を詰めて遊んでいた。
「やめなさい」と言いかけて、ふと手を止めた。
その小石も、きっと何年か後には懐かしく思える。
家は、暮らしとともに呼吸しているのだ。
手を入れるたびに、家が“自分らしく”育っていく

古民家を手直ししながら暮らすと、家と自分の距離が近くなる。
手をかけるたびに、家が“自分の暮らし”に馴染んでいく。
家具の配置を変える、庭の花を植え替える、障子紙を貼り直す。
どんな小さな作業でも、「自分で手を動かした」という実感が残る。
志麻さんも、少しずつ家を直しながら「家が家族のリズムに馴染んでいく」と語っていた。
それは、完成を目指すリフォームとはまったく違う“暮らしの成長”。
昨年、冬の寒さに耐えきれず障子を二重にした。
春が来て外したとき、光の柔らかさにハッとした。
「手を加える」とは、自然の変化に寄り添うことなのだと思う。
家は直すたびに、自分に似てくる。
時間がつくる“味わい”を信じてみる

暮らしの美しさは、新しさよりも“時間”の中に宿る。
古くなることは、価値を失うことではなく、物語を深めること。
志麻さんの古民家も、すべてが新品ではない。
壁のくすみ、木の割れ、鉄鍋の焦げ跡。
どれもが「そこに人がいた証」。
古民家暮らしは、時間を敵にしない生き方だ。
夏の午後、縁側で風鈴が鳴る。
光の加減で柱の色が少しずつ変わっていく。
何も起きないような時間の中で、確かに“生きている”音がする。
その瞬間、「この家と一緒に歳を重ねたい」と思った。
まとめ:暮らしは“完成品”ではなく、“日々の積み重ね”
家も人も、完成を目指す必要はない。
不器用なまま、少しずつ手を加えながら生きていけばいい。
タサン志麻さんの古民家のように、未完成の中にこそ温かさがある。
暮らしを重ねることは、自分を育てること。
この家がどう変わっていくかを楽しみにしながら、また新しい一日を始めよう。
🔗 拡散用情報(SNS・サムネ用)
タサン志麻さんの古民家暮らしに学ぶ、“未完成を楽しむ生き方”。
完璧じゃなくていい。
手を加えながら、時間とともに育つ家。
#タサン志麻 #古民家 #丁寧な暮らし #スローライフ
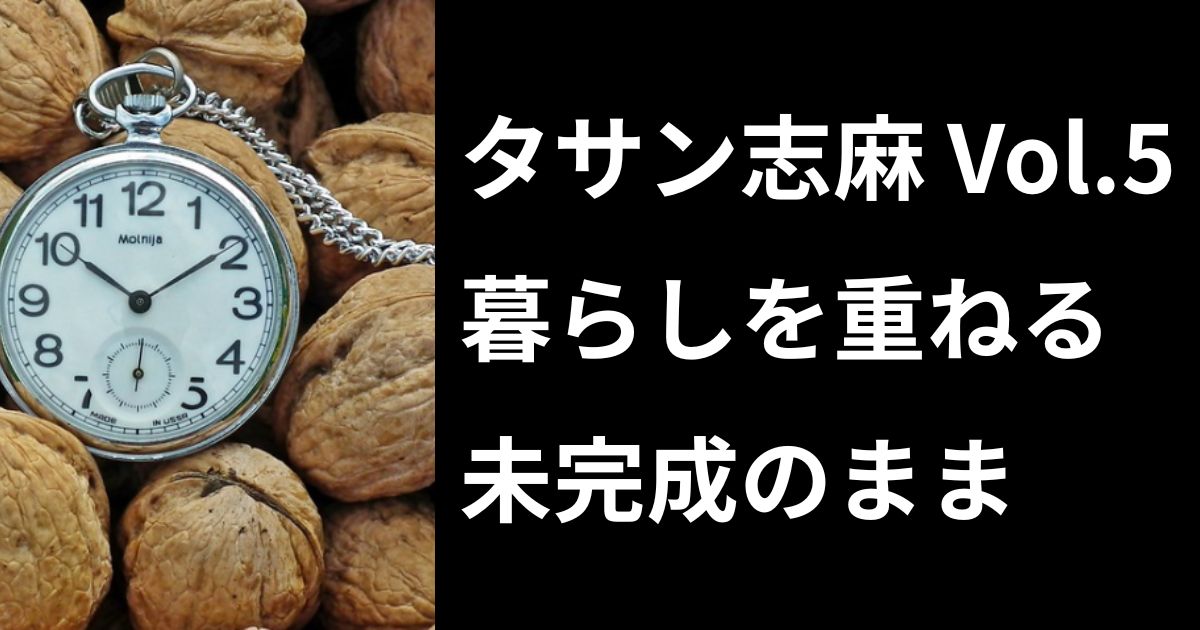
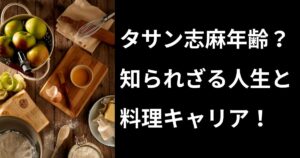


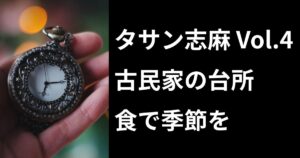
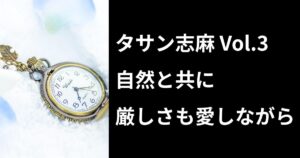
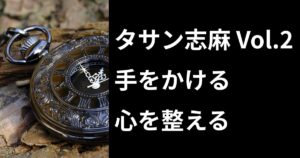
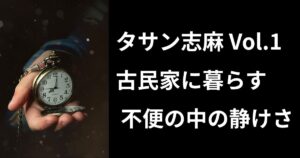
コメント